哲学・思想・社会
『「断熱」が日本を救う 健康、経済、省エネの切り札』 髙橋真樹 著
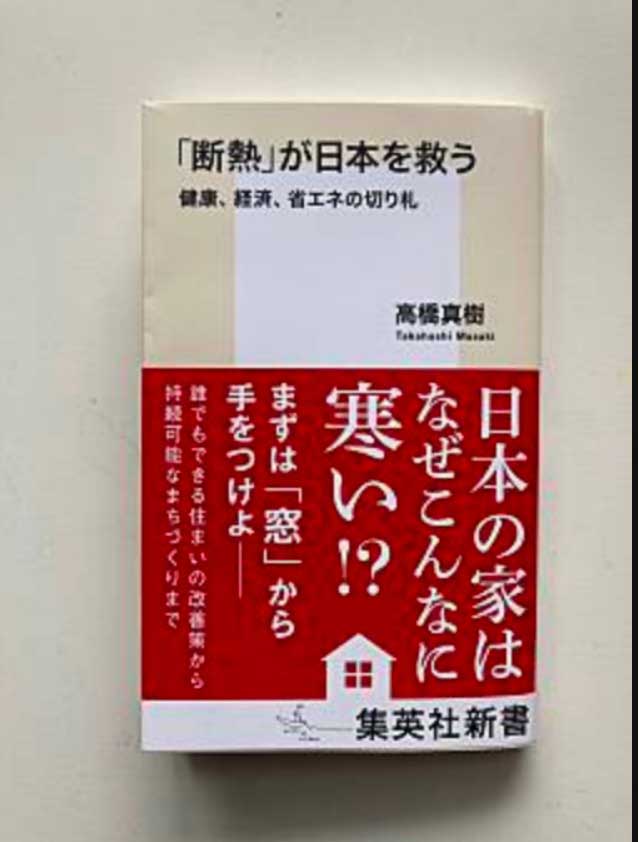 「夏は暑く、冬は寒い」、これが日本の家の常識だと思っていた。兼好法師も「家の作りようは夏をむねとすべし」と言っているではないか…。しかし最近、夏の猛暑・酷暑と冬の冷え込みが耐え難くなっていた。寄る年波のせいだけではなく、温暖化による気候変動にも大いに原因があることは確かだろう。電気代が高くつくが、エアコンしか術はないとあきらめていた。
「夏は暑く、冬は寒い」、これが日本の家の常識だと思っていた。兼好法師も「家の作りようは夏をむねとすべし」と言っているではないか…。しかし最近、夏の猛暑・酷暑と冬の冷え込みが耐え難くなっていた。寄る年波のせいだけではなく、温暖化による気候変動にも大いに原因があることは確かだろう。電気代が高くつくが、エアコンしか術はないとあきらめていた。
読み始めて驚いた。日本の住宅の断熱性能がいかに欧米標準から遅れているか。築19年の猫婆軒は隙間だらけで無断熱の昔ながらの家屋ではない。ペアガラスの窓で断熱材も使用している。24時間換気も行っている。ところがこの程度では違法建築に当たるらしい。アルミサッシも冬寒くなる先進国では使用されないそうだ。
本書の主張はきわめて明白。書き方もストレートで分かりやすい。日本では家族が集まる部屋だけを暖める「間欠暖房」が普通だ。著者によればこれは良くない。他の部屋との寒暖差を生み、むしろヒートショックの原因になるからだ。廊下や寝室、脱衣所、浴室、トイレなども含め家全体を18℃以上に保つことが重要だと言う。実際、データでは北海道や青森県のように家全体を温める住宅が多い地域ほど冬の寒暖差で亡くなる人が少なくなっていることが分かる。
間欠暖房せざるを得ないのは、日本の住宅の断熱性能が悪いからだ。「穴だらけのバケツ」とはうまい例え。いくら水=エネルギーを注ぎ込んでも水はたまらない=家全体が快適な温かさにならない。エネルギーの使い過ぎは電気代がもったいないし電力不足を招く。そこで間欠暖房(冷房)に頼る。「こまめに家電のスイッチを切る」「薄着、厚着でしのぐ」「冷暖房の設定温度を控えめにする」といった「がまんの省エネ」が推奨される。どこかがおかしい。
合理的に考えれば、「穴をふさぐ」しかない。つまり住宅の断熱気密性能を高めることである。ここに「エコハウス」が登場する。著者の定義に従うと、エコハウスとは「エネルギー消費が少なくてもより快適に過ごせる」「健康と家計を守り、脱炭素に貢献できる」住宅である。
著者はエコハウスに引っ越す。2階建ての一般的な戸建て住宅と同じサイズ(約30坪)だ。その快適な住み心地と光熱費については、是非本書を読んでほしい。
日本では35℃を超える教室で子どもたちが勉強させられている。筆者の経験ではエアコンが設置された教室でさえ40℃以上になることもままあった。欧米のように「暑さ寒さは人権問題」という発想が日本の行政には皆無に近いのだ。
日本政府もやっと重い腰を上げ始め、2025年から現在最高とされている断熱等級4を最低基準にし、等級5~7が新設されるそうだ。標準的な戸建てで省エネ基準レベルの等級4(建設費2000万円)から世界レベルの7にアップさせれば初期費用は300万円高くなる。しかし、光熱費は年に14.4万円安く、21年で300万円は償却でき、あとは得になる計算。うーん、なるほど。でもこれから家を建てる(建て替える)人はどれだけいるのだろう?そんな疑問には断熱リノベーションの方法、リフォーム業者の選び方まで示してくれる。窓の改修だけでずいぶん温かくなるとのこと。思いのほか安くできることに気が付くだろう。自治体が補助金を出すなどの取り組みも紹介されている。
バケツの穴をふさぐ、断熱性能を高めることのメリットは、光熱費を押さえることだけではない。もちろん年33.5兆円(2022)もの化石燃料の輸入を大幅に削減し、エネルギー安全保障に貢献し、カーボンニュートラルに寄与することは言うまでもない。それだけではない。住宅の耐用年数と資産価値が高まる。さらに期待できることは健康面だ。起床時の血圧を下げ、脳卒中や心筋梗塞の死亡者を減らす。ケガのリスクが減少し、夜間頻尿、腰痛、睡眠障害、風邪、アレルギー障害、子どもの喘息やアトピー性皮膚炎など、さまざまな健康に関する症状が改善し健康寿命が延びるという報告が出されている。
つまるところ、自己資金に合わせて、できればちょっと背伸びして「断熱」すれば、自分も社会も長持ちしますよ、という大変読みやすい一冊であります。
『アメリカは内戦に向かうのか』 バーバラ・F・ウォルター 著 井坂康志 訳
 「まさかね」「ありえない」と思う、いささかショッキングな書名だ。しかし原題は『HOW CIVIL WARS START AND HOW TO STOP THEM』。アメリカの政治学者によるまともな論考である。
「まさかね」「ありえない」と思う、いささかショッキングな書名だ。しかし原題は『HOW CIVIL WARS START AND HOW TO STOP THEM』。アメリカの政治学者によるまともな論考である。
著者は第二次世界大戦後に勃発した無数の内戦を研究し、どの内戦にも共通する危険因子に着目した。フィリピン、東ティモール、イラク、ユーゴスラビア、ボスニア、北アイルランド、ルワンダ、エチオピア、ウクライナなど、豊富に具体例を示して内戦に至る道筋を明らかにしていく。
専制国家と民主主義国家との中間に位置する国家を研究者は「アノクラシー」と呼んでいる。アノクラシー・ゾーンの国民は多くの場合選挙を通して民主的統治に関与する。一方、権威主義的で多大な権力を独占する大統領などが現れることがある。「非自由主義的民主主義」「部分的民主主義」などと呼ばれ、内戦になる危険性は専制国家の2倍、民主主義国家の3倍に及ぶといわれる。
近年までは専制が打倒されるか、もしくは抗議運動に屈して政権が民主化の受容を余儀なくされるかのどちらかであった。専制から民主主義への移行途上でほとんどの国家が内戦の危険に際会した。しかも民主化が迅速で断固たるものであるほどに内戦リスクが高まっていたのだ。
しかし、2010年以降はそうではない。新たな民主主義国家だけでなく、安定した豊かな民主主義国家でさえ民主主義離れが進んでいる。これらの国の多くでは、選挙で選ばれた政治家が言論の自由自体を攻撃する。憲法を「改正」して権力集中を図った国もあった。代議制政治の弱体化もみられる。指導者が民主主義を保護する「安全装置」を踏み越え、なきがごとく行動するからである。「安全装置」とは、大統領への制約、政府機関間の相互監視と抑制、報道による説明責任の要求、公正かつ公開の政治的競争などである。世界中の民主主義国家を調査・評価しているスウェーデンのⅤ-Dem研究所は2020年に「専制化警報」を発している。
アノクラシーに加えて、「派閥主義」とも呼ぶべき政治的分極の激化が内戦に導く場合が多い。つまり、イデオロギーよりも民族、宗教、人種的なアイデンティティーを共有する政党が他者を排斥し、その犠牲の上に統治しようとする。権力の獲得・維持のために民族的、宗教的ナショナリズムに訴える。彼らは自らと支持者にばかり有利で狭隘な政治的搾取を行い、社会全体を分裂させる。
また、それまで権力の上位にあった人々が「格下げ」され落ちこぼれていくとき、実体的な暴力に走る傾向が一挙に高まる。自ら当然としていた地位を喪失すると人は深く傷つき激しい憤怒に焼かれる。このとき最も危険な派閥が生まれる。
どれほど裏切られ追いつめられようと、人は明日を信じたいと願う存在である。デモや抗議行動は政府が何とかしてくれるという期待があればこそなのだ。しかし、はっきりと希望が死んだとき、もはや他に方法がないと観念した者がやむなく武器を手にする。誘拐、暗殺、爆弾テロ…。内戦の勃発性が高まっていく。
さらに、民族主義仕掛人はSNSを差別と敵意、恐怖と暴力の有効な増幅装置として用いる。誤情報、偽情報、陰謀論、フェイクニュース、ヘイトスピーチ、過激投稿がエンゲージを獲得しやすいことはすでに証明されている。SNSによって民族間の派閥が生まれ、社会的分断が拡大し、移民への憎悪は危険水域に達し、ポピュリストが当選するようになる。規制なきオープンなプラットフォームは内戦にとって完璧な促進条件と化している。内戦とまでいかなくても政府の暴力的キャンペーン、少数民族への一方的攻撃、民族浄化=大虐殺の一形態となっている。
「アメリカは内戦に向かうのか」という問いの答えはこうだ。アメリカ合衆国は現在アノクラシー状態にある。つまり、第2の「南北戦争」を招く危険性があるということだ。分析によれば、内戦に至る10段階の5ないし6段階まで進行していると考えられる。「ありえない」と思っていたことが現実になれば、世界のパワーポリテックスは一体どうなってしまうのだろう?
もちろんアノクラシー状態でも内戦に陥らない国(回避の方法は様々)は存在するが、内戦を回避した国として優れて参考とするべき国として著者は南アフリカ共和国を挙げる。最終章では「内戦を阻むために今なすべきこと」が述べられている。恐ろしい警告の書である。
『誰のために法は生まれた』 木庭 顕 著
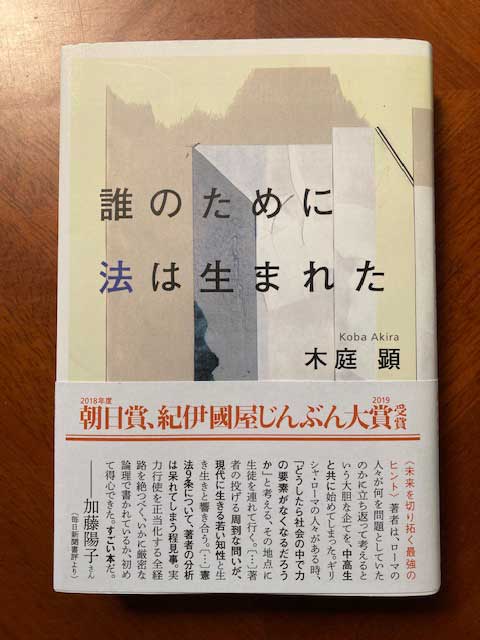 法とは社会の秩序を守るために国が決めたルールで、対立する言い分を平等に聴いて勝ち負けを決めるのが裁判だ、それゆえ法とは保守的なものだ、と思っている人が多いのではないだろうか。実は、私もそう思い込んでいた一人である。
法とは社会の秩序を守るために国が決めたルールで、対立する言い分を平等に聴いて勝ち負けを決めるのが裁判だ、それゆえ法とは保守的なものだ、と思っている人が多いのではないだろうか。実は、私もそう思い込んでいた一人である。
しかし、「見捨てられた一人のためにのみ、連帯(政治あるいはデモクラシー)は成り立つ」と本書は言う。孤立した一人、追いつめられた個人に立ち塞がるものは特定の個別のものではなく、複雑に絡みあった集団や組織や徒党、すなわちがっちりした社会構造である。グルになった権力が暴力的に孤立無援の個人を追いつめていくのを食い止めるために法が生まれたのだ。
このときに非常に大事になるのが「占有」というローマからきた概念で、その質の高さが重要になってくる。占有は個人を犠牲にしようとする集団をブロックする。このあたりを筆者は「授業」で明らかにしていく。中高生に映画を見せ、ローマ喜劇やギリシャ悲劇を、また最高裁判例まで読ませて問いかける。ソクラテス・メソッドというが筆者の解説しすぎが少し気になった。質問は正答に導くためのものではないと思うのだが。書籍化するにあたり仕方なかったのかもしれない。とまれ、反応する若い知性のきらめきがなんともまばゆい。
今年(2022年)公開された「ゴヤの名画と優しい泥棒」という映画がある。孤独な高齢者のためにロンドン・ナショナル・ギャラリーから盗んだゴヤの名画の身代金で公共放送BBCの受信料を肩代わりしようとしたクビになった60歳のタクシー運転手の実話を基にしている。弁護人、陪審員、裁判官がそれぞれ被告の苦痛に共感する想像力を持った個人として連帯し無罪評決にいたるのだ。本書を読んでからこの映画を観ると、「誰のために法は生まれた」というラディカルな問いに答える法精神が欧米には今なお息づいていると実感できる。目からウロコの一冊である。
『ぼくはお金を使わずに生きることにした』 マーク・ボイル 吉田奈緒子訳
 イギリスで1年間お金を使わずに生活する実験をした29歳の若者の記録。
イギリスで1年間お金を使わずに生活する実験をした29歳の若者の記録。
「お金」という道具が生まれた瞬間から消費者と消費されるものとの間の断絶が生まれた。お金のせいで、自分たちが消費する物とも自分たちが使用する製品の作り手とも完全に無関係でいられるようになってしまった。筆者は、貨幣経済を根源から問い直し、「お金がなくても生き延びられる」ではなく「豊かで幸せに暮らせる」ことを証明しようする。
頭の固い原理主義者かと思ったが、そんなことはない。理想主義と現実主義のはざまで考え悩みながら行動している。人類が明日からお金、石油を使うのをやめろとは言わない。使い続けるなら、せめて必要性が低かったり、環境に害を与える物やサービスに使うのはやめよう、今後は、長い目で見て人類を真に持続可能にしてくれるような新しいインフラを構築するために両方の資源を使っていこう、と語りかける。
「世界を変えたければ、まず自分がその変化になりなさい・・・」。ガンジーのことばを著者は実践した。革命ではなく、進化、移行、変容だ。もう少しこの世界に愛情、敬意、気づかいを注ぎこもう、見返りを求めず与えることのすばらしさが本書から伝わってくる。フリーエコノミーの知恵も満載。『無銭経済-金なし生活マニュアル』、続編『ぼくはテクノロジーを使わずに生きることにした』もどうぞ。
『ニュー・アソシエイショニスト宣言』 柄谷行人
 近代のシステムを3つの交換原理・交換様式の視点から見るところが新鮮。現代は資本=ネーション=国家の三位一体がうまく機能しなくなった時代である。ネーションの部分が切り捨てられ、資本=国家が剥き出しになって新自由主義的な政策がとられ、格差が拡大している。しかし「負け組」は連帯できず、闘うこともできない。そんな人が戦闘的になると排外主義的な運動になりがちでポピュリズムに足元をすくわれてしまう。
近代のシステムを3つの交換原理・交換様式の視点から見るところが新鮮。現代は資本=ネーション=国家の三位一体がうまく機能しなくなった時代である。ネーションの部分が切り捨てられ、資本=国家が剥き出しになって新自由主義的な政策がとられ、格差が拡大している。しかし「負け組」は連帯できず、闘うこともできない。そんな人が戦闘的になると排外主義的な運動になりがちでポピュリズムに足元をすくわれてしまう。
資本(商品交換による搾取)と国家(支配・保護の収奪)を超克し、ネーション(互酬交換にもとづく共同体)の高次元の回復はどうすれば可能か。旧来の労働運動では不十分である。非資本主義的な経済空間は、勝ち組になることを放棄した人たちによって形成される。筆者は、それがアソシエーションだと言う。世界変革への新たな宣言。
『日本精神史』<上・下> 長谷川宏
 上巻は三内丸山遺跡から『正法眼蔵』まで。下巻は『新古今和歌集』『愚管抄』から『東海道四谷怪談』まで。
上巻は三内丸山遺跡から『正法眼蔵』まで。下巻は『新古今和歌集』『愚管抄』から『東海道四谷怪談』まで。
日本の美術、思想、文学を人々の精神の歴史としてとらえます。
日本人の精神が多様なうねりを見せつつ近代に向かう、そのダイナミックな流れを鮮やかに浮き彫りにしています。
