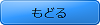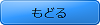
人は、パンのみに生くるにあらず。
されど。
食べることと、生きることとは,
ほぼ同じである。
子供の頃から常々考えていたことは、家を一歩出たら、周囲に食い物があるという生活である。
それは、生活の周囲にある食べ物とは、まず植物である。しかも自然界にある雑草。
それから海草、魚、昆虫、動物。
人手を加えなくても自然界で育つ食用可能な食べ物。
これが人類にとってもっとも重要な資源ではないかということです。
将来の食糧危機にそなえて、公園、街作り、道路、ほか野山、河川に食用になる樹木を考慮した、
都市計画を考えるべきである。
食糧危機に備えて、個人は自己の問題として考える必要がある。
保存食についてもそうです。今あるものの保存食も検討しよう。
10年の保存、5年の保存、3年の保存までは最低必要な検討をしておくべきです。(最近は米国で25年保存も確立されたらしい)
考えすぎでしょうか?
手っ取り早いのは、乾麺です。うどん、そうめん。スパゲッテイー。
正月でなくとも、今はどこにでも売られている餅。
トウモロコシ、大豆、小豆、その他の豆類。
海藻では、昆布、わかめ、ひじきの保存。干しだこ、するめ、貝柱、etcの海産物の長期保存法。
干し椎茸、切り干し大根、キクラゲ、寒天、等の乾燥食品の長期保存。
漬け物の長期保存。
後は調味料、砂糖、氷砂糖、塩、味噌、醤油、カツ節、ソース。あんこ。ようかん。パン、乾パン。焼き芋。
カレー粉、唐辛子、インスタントのスープの素。チーズ、バター、干し肉、瓶詰め。コーヒー豆。
これらの長期保存の方法はどうすればよいか(長期とは最低5年以上を基準とすべきこと)
保存する容器、乾燥剤、温度管理、窒素の封入方法には空気から酸素を取り除く方法のほか冷凍保存も進化している。
粉類(小麦粉、米粉、小豆、大豆、etc)
市販乾燥食品の研究。
簡易真空パックの方法。
そのほかに野菜、穀類や果物の種子の保存。
提案として、TPPなど米を政府が買い付け義務を負った場合は、米を蒸して、乾燥、粉末にしてプレスする、
日本の餅のようにして
マイナス40度以下の低温で冷凍(いわゆるABIシステム)輸送費を別にすれば、南極で保存。
もしくは、刑務所で発電労役を作って地下に保存庫を創設。